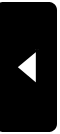2010年01月19日
2010年01月18日
2010年01月05日
備瀬の海岸
■『備瀬の海岸』 沖縄 本部町



自転車を借りて 『福木並木』 をゆっくりと走って来ました。
ここは前回少ししか立ち寄れなかった所だったので、今回はある程度メインに(←自分だけそう思っていた)時間を費やすこととなりました。
自転車で行き止まりまで行くと…きれいな海が広がっていました。
天候にも恵まれ、とてもきれいな海を望むことが出来ました。
本当にきれいな所でしたよ!
ここは確実に時間の流れるスピードが変わっている所です。
とてもゆっくりとしていて贅沢とも感じられる時間が流れています。
『美ら海水族館』 が近くにありますが、こちらは自分としてはどうでもいぃのです。
でも、子供達はそこそこ楽しみにしていたので寄りましたけど…。
時間がちょうど良かったらしくジンベエザメの餌やりを見ることが出来ました。
※ 『福木並木』 の詳細はこちら ⇒ 福木並木
※ 『備瀬の海岸』 の詳細はこちら ⇒ 備瀬崎
備瀬は、本島でも唯一と言えるほど大規模なフクギ林が残っている集落である。そして屈指の美しい海、さらには知る人ぞ知る夕日スポットでもある。人とすれ違う事もほとんどなく、何年も前に時間が止まってしまった様な静謐な空気。
■備瀬崎
知る人ぞ知る、と最近言えなくなってきたほどのスノーケリングポイント。潜らなくても岸からいろいろな種類の熱帯魚が見られる。ニモ(カクレクマノミ)も沢山いたが、心無い人にイソギンチャクごと持ち去られてしまった。漁業権や県漁業調整規則により規制されているので、くれぐれも海洋生物は持ち帰らないようにして欲しい。よいこのみんなは魚を網ですくったりして遊んでも、帰るときは海に帰してあげてね。目の前の島(聖域になっている)へは干潮の時歩いて渡る事ができるが、潮が満ち始めると戻れなくなってナキを見るので注意。また川のように激しく流れる潮流が発生したり、クラゲに刺されたりする事もあるので、小さな子供連れの場合は特に注意が必要だ。尚ここだけの話しだが、探せば星砂が見つかる。自分で見つけたホンモノの星砂は一生の宝物になるでしょう。
※管理されている遊泳場ではないので、AEDは勿論、救急セットもハブクラゲ除けネットもレスキューも、何もない。くれぐれも自己責任で気をつけて楽しんで欲しい。
(20091227旅)



自転車を借りて 『福木並木』 をゆっくりと走って来ました。
ここは前回少ししか立ち寄れなかった所だったので、今回はある程度メインに(←自分だけそう思っていた)時間を費やすこととなりました。
自転車で行き止まりまで行くと…きれいな海が広がっていました。
天候にも恵まれ、とてもきれいな海を望むことが出来ました。
本当にきれいな所でしたよ!
ここは確実に時間の流れるスピードが変わっている所です。
とてもゆっくりとしていて贅沢とも感じられる時間が流れています。
『美ら海水族館』 が近くにありますが、こちらは自分としてはどうでもいぃのです。
でも、子供達はそこそこ楽しみにしていたので寄りましたけど…。
時間がちょうど良かったらしくジンベエザメの餌やりを見ることが出来ました。
※ 『福木並木』 の詳細はこちら ⇒ 福木並木
※ 『備瀬の海岸』 の詳細はこちら ⇒ 備瀬崎
備瀬は、本島でも唯一と言えるほど大規模なフクギ林が残っている集落である。そして屈指の美しい海、さらには知る人ぞ知る夕日スポットでもある。人とすれ違う事もほとんどなく、何年も前に時間が止まってしまった様な静謐な空気。
■備瀬崎
知る人ぞ知る、と最近言えなくなってきたほどのスノーケリングポイント。潜らなくても岸からいろいろな種類の熱帯魚が見られる。ニモ(カクレクマノミ)も沢山いたが、心無い人にイソギンチャクごと持ち去られてしまった。漁業権や県漁業調整規則により規制されているので、くれぐれも海洋生物は持ち帰らないようにして欲しい。よいこのみんなは魚を網ですくったりして遊んでも、帰るときは海に帰してあげてね。目の前の島(聖域になっている)へは干潮の時歩いて渡る事ができるが、潮が満ち始めると戻れなくなってナキを見るので注意。また川のように激しく流れる潮流が発生したり、クラゲに刺されたりする事もあるので、小さな子供連れの場合は特に注意が必要だ。尚ここだけの話しだが、探せば星砂が見つかる。自分で見つけたホンモノの星砂は一生の宝物になるでしょう。
※管理されている遊泳場ではないので、AEDは勿論、救急セットもハブクラゲ除けネットもレスキューも、何もない。くれぐれも自己責任で気をつけて楽しんで欲しい。
(20091227旅)
2009年07月21日
養老天命反転地
■『養老天命反転地』 岐阜 養老町





随分前からちょっと気になっていた所に…ついに行って来ました~!
行くまでその全貌がよく分かりませんでした。
行って見て…う~ん、やっぱりよく分からん…。
でも、少しわくわくして子供時代に戻った様な妙な感じがしました。
※ 説明して理解出来る様な場所ではないので、行って見て体感して下さい。
※ 『養老天命反転地』 の詳細はこちら
⇒ http://www.yoro-park.com/j/rev/
養老天命反転地は、現代美術家荒川修作と、パートナーで詩人のマドリン・ギンズのプロジェクトを実現したテーマパークです。
約18,000m2の園内には、メインパビリオン「極限で似るものの家」とすり鉢状の「楕円形のフィールド」があります。「極限で似るものの家」は岐阜県の形をした屋根を持つ迷路状の建物で、天井、地上、地下の3層にそれぞれ家具が取り付けられています。「楕円形のフィールド」には、この「極限で似るものの家」を分割したパビリオンが点在するほか、148の曲がりくねった回遊路や、大小さまざまの日本列島が配されています。
ここでは、予想もつかなかった風景や懐かしい風景、いろいろな出来事に出会うことになるでしょう。はじめて体験する世界で、新しい自分を発見できるかもしれません。
園内はすべて斜面で構成されていますので、ゴム底靴など身軽な服装が適しています。
ペットの持ち込み、園内での食事はご遠慮ください。また、ゴミのお持ち帰りにご協力ください。
■芸術家/建築家の荒川修作+マドリン・ギンズはこんな作品も創っています。
『三鷹天命反転住宅』
⇒ http://www.architectural-body.com/mitaka/
三鷹天命反転住宅 In Memory of Helen Keller は、芸術家/建築家の荒川修作+マドリン・ギンズによる、世界で最初に完成した「死なないための住宅」です。
(20090720旅)





随分前からちょっと気になっていた所に…ついに行って来ました~!
行くまでその全貌がよく分かりませんでした。
行って見て…う~ん、やっぱりよく分からん…。
でも、少しわくわくして子供時代に戻った様な妙な感じがしました。
※ 説明して理解出来る様な場所ではないので、行って見て体感して下さい。
※ 『養老天命反転地』 の詳細はこちら
⇒ http://www.yoro-park.com/j/rev/
養老天命反転地は、現代美術家荒川修作と、パートナーで詩人のマドリン・ギンズのプロジェクトを実現したテーマパークです。
約18,000m2の園内には、メインパビリオン「極限で似るものの家」とすり鉢状の「楕円形のフィールド」があります。「極限で似るものの家」は岐阜県の形をした屋根を持つ迷路状の建物で、天井、地上、地下の3層にそれぞれ家具が取り付けられています。「楕円形のフィールド」には、この「極限で似るものの家」を分割したパビリオンが点在するほか、148の曲がりくねった回遊路や、大小さまざまの日本列島が配されています。
ここでは、予想もつかなかった風景や懐かしい風景、いろいろな出来事に出会うことになるでしょう。はじめて体験する世界で、新しい自分を発見できるかもしれません。
園内はすべて斜面で構成されていますので、ゴム底靴など身軽な服装が適しています。
ペットの持ち込み、園内での食事はご遠慮ください。また、ゴミのお持ち帰りにご協力ください。
■芸術家/建築家の荒川修作+マドリン・ギンズはこんな作品も創っています。
『三鷹天命反転住宅』
⇒ http://www.architectural-body.com/mitaka/
三鷹天命反転住宅 In Memory of Helen Keller は、芸術家/建築家の荒川修作+マドリン・ギンズによる、世界で最初に完成した「死なないための住宅」です。
(20090720旅)
2009年01月05日
慶佐次のヒルギ林
■『慶佐次のヒルギ林』 沖縄 東村


今回は 『やんばるのマングローブ』 の入口だけを見て来ました。
子供がもう少し大きくなってくればカヌー体験は是非ともしたい!
カヌーといえば…社会人になりたての頃、車に着ける専用のキャリアを買ったが、お金が無くて出来なかった辛い過去があります。(泣)
そんなにドカドカと林の中に入っていかなくてもいい。
そーっと雰囲気を感じ取れさえすればいいのです。
何年か後が楽しみです。
数年後でも…ハブはイヤだ! ヤンバルクイナは歓迎です!
※ 『慶佐次のヒルギ林』 の詳細はこちら ⇒ 慶佐次のヒルギ林
慶佐次(げさし)湾の河口から上流に向かって発達した、ここ慶佐次川のヒルギ林は、沖縄本島では最も規模が大きく、10haにオヒルギ、メヒルギ、ヤエヤマヒルギなどが生え、中でもヤエヤマヒルギは分布の北限にあたることから、大切に保護するため昭和34年(1959)年12月6日に、当時の琉球政府の天然記念物に指定されました。
そして、沖縄の祖国復帰により、昭和47年5月15日に国の天然記念物に指定されました。さらに、平成5年4月1日には、東村が誕生して70歳の誕生日を記念して「ヒルギ」が村の木に指定されました。
(20081223旅)


今回は 『やんばるのマングローブ』 の入口だけを見て来ました。
子供がもう少し大きくなってくればカヌー体験は是非ともしたい!
カヌーといえば…社会人になりたての頃、車に着ける専用のキャリアを買ったが、お金が無くて出来なかった辛い過去があります。(泣)
そんなにドカドカと林の中に入っていかなくてもいい。
そーっと雰囲気を感じ取れさえすればいいのです。
何年か後が楽しみです。
数年後でも…ハブはイヤだ! ヤンバルクイナは歓迎です!
※ 『慶佐次のヒルギ林』 の詳細はこちら ⇒ 慶佐次のヒルギ林
慶佐次(げさし)湾の河口から上流に向かって発達した、ここ慶佐次川のヒルギ林は、沖縄本島では最も規模が大きく、10haにオヒルギ、メヒルギ、ヤエヤマヒルギなどが生え、中でもヤエヤマヒルギは分布の北限にあたることから、大切に保護するため昭和34年(1959)年12月6日に、当時の琉球政府の天然記念物に指定されました。
そして、沖縄の祖国復帰により、昭和47年5月15日に国の天然記念物に指定されました。さらに、平成5年4月1日には、東村が誕生して70歳の誕生日を記念して「ヒルギ」が村の木に指定されました。
(20081223旅)
2008年12月27日
やちむんの里-1
■『やちむんの里』 沖縄 読谷村





ここは前回訪れることが出来なかった場所です。
今回、大人の楽しみ・テーマとして 『気に入った焼物があったら買って来よう!』 ということがありました。
なるほど…この地域全体が焼物の村といった感じでした。
この里の入口にはきれいな駐車場が整備されていて、里内は歩いて散策をすることが出来ます。
焼物に興味のある方だったら半日では足りないかもしれません…。
うちは小さい子がいるから、1時間程でちょこっと廻って気に入った物を買って来ました。 (雨もパラパラしていたし…)
購入した物は、頑なな伝統を受け継いでいる物とは少し違って伝統を受け継ぎつつもポップ感を感じられる物です。
事務所&家にお越しの際はこの器でお茶を入れさせて頂くかもしれません…楽しみにしていて下さい!
※ 『やちむんの里』 の詳細はこちら ⇒ やちむんの里
「やちむん」とは沖縄で焼物のことで、やちむんの里は陶芸家の方々が集まってできました。里では作品を作っているところを見ることができたり、やちむんの販売や、やちむんの器で食事をとることもできます。自然に囲まれた美術館にいるような感じがします。
■沖縄の焼物は、力強く暖かいものが多いです。
1682年の頃、琉球王朝の尚貞王は、各地に点在した窯場を壺屋に集めて陶業の進行を図りました。そして、今まであった技術に加え、日本、中国各地の技術を吸収しながら多彩な焼き物を作っていきます。
現在でも、那覇の壺屋には多くの焼き物やが軒を並べ、登り窯の跡などもあり、当時の繁栄を時間を超えて垣間見る事が出来ます。
ただ、最近では住宅が密集してきたので、焼き物を焼くには環境的に無理が生じてきたために窯場は読谷村の座喜味城跡の近くにあるやちむんの里の方に移っています。
人間国宝の金城次郎氏が招致され、「やちむんの里」構想に何人かの陶芸家達が共同登り窯をつくり、その後若手の陶工が読谷山焼「北窯」として独立、現在は何軒のも工房が立ち並び、各々売店、展示場などが併設されて週末には、この山間の里に来る人々も増えています。
(20081225旅)





ここは前回訪れることが出来なかった場所です。
今回、大人の楽しみ・テーマとして 『気に入った焼物があったら買って来よう!』 ということがありました。
なるほど…この地域全体が焼物の村といった感じでした。
この里の入口にはきれいな駐車場が整備されていて、里内は歩いて散策をすることが出来ます。
焼物に興味のある方だったら半日では足りないかもしれません…。
うちは小さい子がいるから、1時間程でちょこっと廻って気に入った物を買って来ました。 (雨もパラパラしていたし…)
購入した物は、頑なな伝統を受け継いでいる物とは少し違って伝統を受け継ぎつつもポップ感を感じられる物です。
事務所&家にお越しの際はこの器でお茶を入れさせて頂くかもしれません…楽しみにしていて下さい!
※ 『やちむんの里』 の詳細はこちら ⇒ やちむんの里
「やちむん」とは沖縄で焼物のことで、やちむんの里は陶芸家の方々が集まってできました。里では作品を作っているところを見ることができたり、やちむんの販売や、やちむんの器で食事をとることもできます。自然に囲まれた美術館にいるような感じがします。
■沖縄の焼物は、力強く暖かいものが多いです。
1682年の頃、琉球王朝の尚貞王は、各地に点在した窯場を壺屋に集めて陶業の進行を図りました。そして、今まであった技術に加え、日本、中国各地の技術を吸収しながら多彩な焼き物を作っていきます。
現在でも、那覇の壺屋には多くの焼き物やが軒を並べ、登り窯の跡などもあり、当時の繁栄を時間を超えて垣間見る事が出来ます。
ただ、最近では住宅が密集してきたので、焼き物を焼くには環境的に無理が生じてきたために窯場は読谷村の座喜味城跡の近くにあるやちむんの里の方に移っています。
人間国宝の金城次郎氏が招致され、「やちむんの里」構想に何人かの陶芸家達が共同登り窯をつくり、その後若手の陶工が読谷山焼「北窯」として独立、現在は何軒のも工房が立ち並び、各々売店、展示場などが併設されて週末には、この山間の里に来る人々も増えています。
(20081225旅)
2008年12月27日
古宇利島
■『古宇利島』(こうりじま) 沖縄 今帰仁村




古宇利大橋が有名です。
ここは沖縄を紹介した雑誌の表紙とかにもよく使われています。
以前から気になっていたスポットなのですが、今まで一度も行ったことがありませんでした…。
車でこの橋が見える所へ出ると、思わず 『ワ~ッ』 と声を出してしまうことでしょう。
当日はあいにくの曇り空でしたが、十分にその景色を楽しむことが出来ました。
でも…多分、晴れていたらもっと感動したことでしょう!
橋のたもとの海岸でサンゴを拾い、両手にとって砂みたいに落としてみると、カラカラカラッと心地良い音がしましたよ!
島を1周まわって見たら、風情のある景色を観ることが出来ました。
コレといったものはありませんが、美しい景色は何物にも代えられないものだと感じました。
大切にしていきたい風景ですね。
※ 『古宇利島』 の詳細はこちら ⇒ 古宇利島
古宇利(こうり)島は半径約1Km、周囲が約8kmあり、漁業と農業が盛んな島です。古宇利大橋を渡り始めるときれいな海が広がり思わず声が出てしまうほどきれいです。島内はのどかでサトウキビ畑が広がり、昔ながらの沖縄の家が建ち並んでいます。映画やCMのロケ地としても有名です。
古宇利大橋が開通して島外の人もアクセスしやすくなり、週末にもなると島内はにぎやかになります。また、食堂もありますので食事をすることも出来ます。
橋の近くにきれいなビーチがあり、パラソルなどのレンタルも行っていますので海水浴を楽しむこともできます。また、シュノーケルツアーなども体験できるショップもあります。(下記参照)
お願いがあるのですが、民家周辺の道は狭く、車でそこへ入ると島の人に迷惑をかけてしまいますので、入らないようにして下さいね。島を一周できる古宇利一周線があり、10分ほどで一周できますのでそちらもお勧めです。これといってなにもありませんが、沖縄らしい雰囲気や景色を体験したい方にはおすすめです(晴れた日を狙っていくといいですよ)。
(20081223旅)




古宇利大橋が有名です。
ここは沖縄を紹介した雑誌の表紙とかにもよく使われています。
以前から気になっていたスポットなのですが、今まで一度も行ったことがありませんでした…。
車でこの橋が見える所へ出ると、思わず 『ワ~ッ』 と声を出してしまうことでしょう。
当日はあいにくの曇り空でしたが、十分にその景色を楽しむことが出来ました。
でも…多分、晴れていたらもっと感動したことでしょう!
橋のたもとの海岸でサンゴを拾い、両手にとって砂みたいに落としてみると、カラカラカラッと心地良い音がしましたよ!
島を1周まわって見たら、風情のある景色を観ることが出来ました。
コレといったものはありませんが、美しい景色は何物にも代えられないものだと感じました。
大切にしていきたい風景ですね。
※ 『古宇利島』 の詳細はこちら ⇒ 古宇利島
古宇利(こうり)島は半径約1Km、周囲が約8kmあり、漁業と農業が盛んな島です。古宇利大橋を渡り始めるときれいな海が広がり思わず声が出てしまうほどきれいです。島内はのどかでサトウキビ畑が広がり、昔ながらの沖縄の家が建ち並んでいます。映画やCMのロケ地としても有名です。
古宇利大橋が開通して島外の人もアクセスしやすくなり、週末にもなると島内はにぎやかになります。また、食堂もありますので食事をすることも出来ます。
橋の近くにきれいなビーチがあり、パラソルなどのレンタルも行っていますので海水浴を楽しむこともできます。また、シュノーケルツアーなども体験できるショップもあります。(下記参照)
お願いがあるのですが、民家周辺の道は狭く、車でそこへ入ると島の人に迷惑をかけてしまいますので、入らないようにして下さいね。島を一周できる古宇利一周線があり、10分ほどで一周できますのでそちらもお勧めです。これといってなにもありませんが、沖縄らしい雰囲気や景色を体験したい方にはおすすめです(晴れた日を狙っていくといいですよ)。
(20081223旅)
2008年12月26日
ルネッサンス オキナワ
■『ルネッサンスリゾート オキナワ』 沖縄 恩納村



『Club Savvy』 はお勧めです!
ホテルの中だけで楽しめるプログラムがいっぱいです。
ちょっと例を上げるだけでも…
・お風呂は温泉です。
・ホテルの敷地内でイルカショーをやっています。 (ホテルでなんとイルカを飼っている。)
・お昼は基本的に無料です。(美味しい料理です。)
・子供には季節柄 『お菓子の国』 を開催しています。
・聖歌隊・ゴスペル隊等の歌を聴くことが出来ます。
・ホテル内ではサンタさんが 『メリークリスマス! フォッ フォッ フォッ!』 と言いながらウロウロしています。
※その他、マリンプログラムも充実しています。
沖縄本島の中心部に位置している為、どこへ行くにもアクセスが良く、ベースとして最適です。
※ 『ルネッサンスリゾートオキナワ』 の詳細はこちら ⇒ ルネッサンスリゾートオキナワ
詳細は省きます。いいところなので、是非行ってみて下さい!
(20081224旅)



『Club Savvy』 はお勧めです!
ホテルの中だけで楽しめるプログラムがいっぱいです。
ちょっと例を上げるだけでも…
・お風呂は温泉です。
・ホテルの敷地内でイルカショーをやっています。 (ホテルでなんとイルカを飼っている。)
・お昼は基本的に無料です。(美味しい料理です。)
・子供には季節柄 『お菓子の国』 を開催しています。
・聖歌隊・ゴスペル隊等の歌を聴くことが出来ます。
・ホテル内ではサンタさんが 『メリークリスマス! フォッ フォッ フォッ!』 と言いながらウロウロしています。
※その他、マリンプログラムも充実しています。
沖縄本島の中心部に位置している為、どこへ行くにもアクセスが良く、ベースとして最適です。
※ 『ルネッサンスリゾートオキナワ』 の詳細はこちら ⇒ ルネッサンスリゾートオキナワ
詳細は省きます。いいところなので、是非行ってみて下さい!
(20081224旅)
2008年10月28日
遠州横須賀-3
■『井戸』 掛川市(旧大須賀町)


思わず立ち止まってしまいました。
というか、おばさん達が何か立ち止まって見ていたので、自分も立ち止まってしまったわけでありまして…。
案内の立ち札も掛かっており、以前からこの様にオープンにされていた様子です。
普通は気づかずに通り過ぎてしまう様なスポットで、自分はまったく知りませんでした。
おそらくこの街にはこの様な井戸がたくさんあったことでしょうし、まだ現存しているものがたくさんあるのかもしれません。
時代を超えて井戸端会議の話し声が聞こえてくる様なそんな気がする場所でした。
この奥には、古くから共同使用のつるべ井戸があり、清潔にして美しい水が豊富に湧いておりました。
ここは井戸に通じる道として 『井戸道』 と呼ばれてきました。
家と家に挟まれたこの小さな空間は、昔から大人たちの井戸端会議の話し声が絶えずまた子供たちが独楽を廻したり、竹馬をするなど、遊びの格好の場所となりました。
『横須賀の街並みを考える会』 十六軒町
※ 『井戸』 の詳細はこちら ⇒ 井戸と風俗
~井戸は、戸別に置かれる場合もあるが、高価であるため、集落の中では数戸単位で設置されることが多い。この場合、生活の一部である井戸端は格好の会話の場所となった。また、井戸には水を汲み出して行う大規模な清掃が必要であり、これを井戸替え、井戸浚え(いどさらえ)、晒井戸(さらしいど)などと呼ぶ。井戸替えも専門の業者が行う他、使用者が共同で当たり地域における夏の年中行事として行なわれる。
水は生活にとって欠かせないものであり、それを汲み上げる井戸は重要視された。日本においては井戸神として弥都波能売神(みづはのめのかみ、水神)などが祀られた。井戸の中に鯉などが放たれていることもある。魚が棲めるということは水が清いということである。この魚を井戸神とみなす地方もあり、井戸の魚はとってはいけないとされる。イモリも井戸を守る「井守」から来ているという説がある。禁忌も多くあり、例えばむやみに井戸を覗き込んではいけないとされた。
その一方で、地下の黄泉に繋がる異界への入り口とも考えられていた。幽霊が出るなどはその一例である。また平安時代に小野篁が井戸を通って地獄に通ったとされる伝説も有名。最近では鈴木光司によるホラー小説『リング』があり、井戸が作品のキーポイントとなっている。
「井戸に毒を入れた」という表現・流言があるように電気・ガスなどがない時代においてライフラインの根幹を破壊する行為の象徴として井戸は位置づけられている。~
(20081026旅)


思わず立ち止まってしまいました。
というか、おばさん達が何か立ち止まって見ていたので、自分も立ち止まってしまったわけでありまして…。
案内の立ち札も掛かっており、以前からこの様にオープンにされていた様子です。
普通は気づかずに通り過ぎてしまう様なスポットで、自分はまったく知りませんでした。
おそらくこの街にはこの様な井戸がたくさんあったことでしょうし、まだ現存しているものがたくさんあるのかもしれません。
時代を超えて井戸端会議の話し声が聞こえてくる様なそんな気がする場所でした。
この奥には、古くから共同使用のつるべ井戸があり、清潔にして美しい水が豊富に湧いておりました。
ここは井戸に通じる道として 『井戸道』 と呼ばれてきました。
家と家に挟まれたこの小さな空間は、昔から大人たちの井戸端会議の話し声が絶えずまた子供たちが独楽を廻したり、竹馬をするなど、遊びの格好の場所となりました。
『横須賀の街並みを考える会』 十六軒町
※ 『井戸』 の詳細はこちら ⇒ 井戸と風俗
~井戸は、戸別に置かれる場合もあるが、高価であるため、集落の中では数戸単位で設置されることが多い。この場合、生活の一部である井戸端は格好の会話の場所となった。また、井戸には水を汲み出して行う大規模な清掃が必要であり、これを井戸替え、井戸浚え(いどさらえ)、晒井戸(さらしいど)などと呼ぶ。井戸替えも専門の業者が行う他、使用者が共同で当たり地域における夏の年中行事として行なわれる。
水は生活にとって欠かせないものであり、それを汲み上げる井戸は重要視された。日本においては井戸神として弥都波能売神(みづはのめのかみ、水神)などが祀られた。井戸の中に鯉などが放たれていることもある。魚が棲めるということは水が清いということである。この魚を井戸神とみなす地方もあり、井戸の魚はとってはいけないとされる。イモリも井戸を守る「井守」から来ているという説がある。禁忌も多くあり、例えばむやみに井戸を覗き込んではいけないとされた。
その一方で、地下の黄泉に繋がる異界への入り口とも考えられていた。幽霊が出るなどはその一例である。また平安時代に小野篁が井戸を通って地獄に通ったとされる伝説も有名。最近では鈴木光司によるホラー小説『リング』があり、井戸が作品のキーポイントとなっている。
「井戸に毒を入れた」という表現・流言があるように電気・ガスなどがない時代においてライフラインの根幹を破壊する行為の象徴として井戸は位置づけられている。~
(20081026旅)
タグ :街並
2008年10月27日
遠州横須賀-2
■『栄醤油』 掛川市(旧大須賀町)






まず、たたずまいがいいでしょ!
とてもいい雰囲気を醸し出している建物です。
現在、『栄醤油』 の醤油を使っているので新たに買うことはなかったのですが、内部を公開していたのでのぞいてみることにしました。
建物の中は醤油の香りが漂い、よくTVで観る樽が置いてあり、『あ~ここで醤油って造られているんだ~』 と今まで頭でイメージしていたものと実物が一致してちょっと感動しました。
なにも小豆島に行かなくても見られるのです。
職人さんが樽の状況や工程、生醤油と醤油の違いなど親切に説明して下さり、とても親しみを感じることが出来ました。
これから買うには、ここまで来てここのお店で買うようにしたいと思っています。
※ 『栄醤油』 の詳細はこちら ⇒ 栄醤油
創業は江戸時代寛政七年からの醤油醸造元です。
現在七代目になります。作り方は昔とあまり変わっていません。
その”お醤油のできるまで”の紹介と”商品の説明”です。
そして城下町遠州横須賀の紹介と町内のおもしろい店等々。
(20081026旅)






まず、たたずまいがいいでしょ!
とてもいい雰囲気を醸し出している建物です。
現在、『栄醤油』 の醤油を使っているので新たに買うことはなかったのですが、内部を公開していたのでのぞいてみることにしました。
建物の中は醤油の香りが漂い、よくTVで観る樽が置いてあり、『あ~ここで醤油って造られているんだ~』 と今まで頭でイメージしていたものと実物が一致してちょっと感動しました。
なにも小豆島に行かなくても見られるのです。
職人さんが樽の状況や工程、生醤油と醤油の違いなど親切に説明して下さり、とても親しみを感じることが出来ました。
これから買うには、ここまで来てここのお店で買うようにしたいと思っています。
※ 『栄醤油』 の詳細はこちら ⇒ 栄醤油
創業は江戸時代寛政七年からの醤油醸造元です。
現在七代目になります。作り方は昔とあまり変わっていません。
その”お醤油のできるまで”の紹介と”商品の説明”です。
そして城下町遠州横須賀の紹介と町内のおもしろい店等々。
(20081026旅)
タグ :街並
2008年10月27日
遠州横須賀-1
■『遠州横須賀』 掛川市(旧大須賀町)





今回、『遠州横須賀街道ちっちゃな文化展』 というイベントで、身近にあった 『横須賀』 という街を歩いてゆっくりと見物することが出来ました。
こんな風にこの街を眺めることは今までありませんでした。
通りに面する家々のご協力もあり、家の中に入って様々な作品を見ることが出来ました。
この庇がどうのこうのとか、ここがこうだからいいんですよ!とかそういう説明は一切不要である。
そこに訪れる人にとっては住む人達の生活・文化・伝統を垣間見ることが出来て、そこに住む人にとってはみんなでイベントを通して繋がっているというコミュニティーの健全さを感じ、展示される作家さんと住人さんとの間では新たな出会いや絆を深めることが出来て、様々な人にとってとても良いイベントだと感じました。
是非、来年も来ようと思いましたね。
とても風情があり、また楽しくもありました。
感謝です!
※ 『遠州横須賀』 の詳細はこちら ⇒ 遠州横須賀街道ちっちゃな文化展
全国の芸術作品が遠州横須賀に集合!
「ちっちゃな文化展」は、横須賀地区に残る古き良き町並みをそっくりそのまま美術館にしてしまおうというイベントです。今年も全国の作家の方々の手によるバラエティ豊かな芸術作品が、町のいたるところに飾られます。
また、町内の名人たちによる技披露をはじめ、コンサートや城下町骨董市などの協賛イベントも催されます。
テーマは「町並みと美の晴れ舞台」
この「ちっちゃな文化展」の特徴の1つは、普段生活しているお宅の軒先や部屋、土間を借りてイベントが催されるところにあります。このイベントは、文化展を主催する遠州横須賀倶楽部の15年以上に渡る地道な努力と、それに賛同し応援する多くの人たちの心意気なくしては成り立ちません。
美しい町並みとすばらしい芸術作品の数々、そして人情味あふれるここ遠州横須賀に来てみませんか。
(20081026旅)





今回、『遠州横須賀街道ちっちゃな文化展』 というイベントで、身近にあった 『横須賀』 という街を歩いてゆっくりと見物することが出来ました。
こんな風にこの街を眺めることは今までありませんでした。
通りに面する家々のご協力もあり、家の中に入って様々な作品を見ることが出来ました。
この庇がどうのこうのとか、ここがこうだからいいんですよ!とかそういう説明は一切不要である。
そこに訪れる人にとっては住む人達の生活・文化・伝統を垣間見ることが出来て、そこに住む人にとってはみんなでイベントを通して繋がっているというコミュニティーの健全さを感じ、展示される作家さんと住人さんとの間では新たな出会いや絆を深めることが出来て、様々な人にとってとても良いイベントだと感じました。
是非、来年も来ようと思いましたね。
とても風情があり、また楽しくもありました。
感謝です!
※ 『遠州横須賀』 の詳細はこちら ⇒ 遠州横須賀街道ちっちゃな文化展
全国の芸術作品が遠州横須賀に集合!
「ちっちゃな文化展」は、横須賀地区に残る古き良き町並みをそっくりそのまま美術館にしてしまおうというイベントです。今年も全国の作家の方々の手によるバラエティ豊かな芸術作品が、町のいたるところに飾られます。
また、町内の名人たちによる技披露をはじめ、コンサートや城下町骨董市などの協賛イベントも催されます。
テーマは「町並みと美の晴れ舞台」
この「ちっちゃな文化展」の特徴の1つは、普段生活しているお宅の軒先や部屋、土間を借りてイベントが催されるところにあります。このイベントは、文化展を主催する遠州横須賀倶楽部の15年以上に渡る地道な努力と、それに賛同し応援する多くの人たちの心意気なくしては成り立ちません。
美しい町並みとすばらしい芸術作品の数々、そして人情味あふれるここ遠州横須賀に来てみませんか。
(20081026旅)
タグ :街並
2008年10月26日
通天閣
■『通天閣』 大阪


CMAの総会の後、大阪の仲間に連れて行って頂いた大阪の名所です。
『通天閣』 から放射状に伸びる何本かの道はそれぞれでまったく違った表情を見せてくれます。
イヤイヤイヤ…見ていて実に面白い!
以外や以外、地元の人はこの辺りにはあまり来ないそうである。
どうやら、『何だか最近きれいになったそうやで~』 ⇒ 『へ~そうなんや~』 で話は終わってしまうらしい。
何年か前までは本当にここは柄が悪くて、とても行く気にはならなかった場所だったとのこと。
大阪の人の方が、その代わり映えを見てある意味カルチャーショックを受けていました。
『や~、来て良かったわ~!これなら案内できるわ~。いいわ~!』 とおっしゃっていました…。
※連れて行って頂きまして、有難うございました。
ちなみに、今回は 『通天閣』 も人気があって入れませんでした。
いつか、来ようっと!
※ 『通天閣』 の詳細はこちら ⇒ 通天閣
通天閣とは、天に通ずる高い建物という意味です。地上103m、360度のパノラマ展望台は、大阪の街を一望できるすばらしい眺め・・・大阪の夜景を楽しむのもロマンチックな気持ちになるだろうね。ビリケンさんの像も通天閣に行ったら、「足を掻いて」願い事をしてください。合格祈願・縁結びなどの神様なんです。通天閣の売店にはビリケンさんのおみやげがいっぱいでした。そして通天閣周辺では、じゃんじゃん横丁という大阪昔ならではの下町商店街があります。そこには名物の串かつやどて焼き屋さんが並んでいます。是非食べに行ってほしい探検スポット!
(20081025旅)


CMAの総会の後、大阪の仲間に連れて行って頂いた大阪の名所です。
『通天閣』 から放射状に伸びる何本かの道はそれぞれでまったく違った表情を見せてくれます。
イヤイヤイヤ…見ていて実に面白い!
以外や以外、地元の人はこの辺りにはあまり来ないそうである。
どうやら、『何だか最近きれいになったそうやで~』 ⇒ 『へ~そうなんや~』 で話は終わってしまうらしい。
何年か前までは本当にここは柄が悪くて、とても行く気にはならなかった場所だったとのこと。
大阪の人の方が、その代わり映えを見てある意味カルチャーショックを受けていました。
『や~、来て良かったわ~!これなら案内できるわ~。いいわ~!』 とおっしゃっていました…。
※連れて行って頂きまして、有難うございました。
ちなみに、今回は 『通天閣』 も人気があって入れませんでした。
いつか、来ようっと!
※ 『通天閣』 の詳細はこちら ⇒ 通天閣
通天閣とは、天に通ずる高い建物という意味です。地上103m、360度のパノラマ展望台は、大阪の街を一望できるすばらしい眺め・・・大阪の夜景を楽しむのもロマンチックな気持ちになるだろうね。ビリケンさんの像も通天閣に行ったら、「足を掻いて」願い事をしてください。合格祈願・縁結びなどの神様なんです。通天閣の売店にはビリケンさんのおみやげがいっぱいでした。そして通天閣周辺では、じゃんじゃん横丁という大阪昔ならではの下町商店街があります。そこには名物の串かつやどて焼き屋さんが並んでいます。是非食べに行ってほしい探検スポット!
(20081025旅)
2008年10月26日
じゃんじゃん通り
■『じゃんじゃん通り』 大阪



CMAの総会の後、大阪の仲間に連れて行って頂いた所です。
いや~いいですよ!
ここまで看板が道路にはみ出しているのは…。
それと、外壁という外壁全てが看板というのも迫力があっていいですよ!
ここまでいくともうアートの世界ですね。
威勢いいね。
こういうの好きです!
中途半端じゃなくて!
※ 『じゃんじゃん通り』 の詳細はこちら ⇒ 新世界編・ジャンジャン横丁
新世界公園通り商店街04・平野屋
大阪の正統派・立ち飲みの「平野屋」、営業中の姿です。
■ジャンジャン横丁・千成屋コーヒー
「なぜかこの手の商店街にはこの手のコーヒー店が必ずあります。そしてまたこの手のコーヒー店は必ず美味しい珈琲があります!」というのが商店街の定理です。この「角ゴシック」の愛想のない看板を見てください!シンプルイズベストです!
■ジャンジャン横丁・串かつ
ジャンジャン横丁と言えば2度漬け禁止の「串かつ」が有名です。特にこの商店街の「ちとせ」や「八重勝」は新世界正統派の串かつ店として古くから営業を続けています。よく見ればこの看板の「身体に優しい植物油を使用」には時代の趨勢を感じます。多分終戦後は、「身体に悪いから串かつは植物油で!」なんて事は夢にも考えなかったでしょうね!生きて行くだけで大変だったのですから。
■ジャンジャン横丁・王将
かの有名な坂田三吉が通っていた将棋会所です。この種のゲーセンの原型は囲碁・スマートボール等がこの商店街にあり、少し他の商店街とは異なる成り立ちを持っているようです。
※どちらかというと東京は浅草に近い雰囲気です!
店舗は閉鎖的ではなく外から観戦することが可能なつくりで、賭け将棋などが出来にくいシステムだと推測されます。ともかく客の年齢層が50歳以上で完璧な「シルバーゲーセン」です。
■ジャンジャン横丁・ホルモン道場
ここでも大阪闇市を発祥とする「ホルモン焼店」が存在し興味深い!この地区の事を時代の生き証人の高齢者に聞いてみるとやはり第2次大戦の空襲にて通天閣より南のこの地区一帯が焼夷弾にて被災したようで、どちらかといえば「ホルモン」とか「串かつ」や「すいとん」と言った飲食のバラック小屋が中心の小規模の闇市(闇飲食街)であったようです。
■新世界公園通商店街03・平野屋
新世界では知らない人のいない居酒屋の名店「平野屋」この日も夕刻からの開業で、昼間はこんな風ですが夜には立ち飲み客で店はあふれ帰ります。価格はリーズナブルな上に味のいい、大人の居酒屋です。やはり老舗は落ち着いている!
■新世界公園本通商店街02
この色彩感覚には驚きます。原色の洪水です!ここまで強烈なデザインが連続すると、かえって目立たないのではと言う気がします。人はこれを「大阪的デザイン」と言いますが果たして本当にそうなんでしょうか?この強烈な店舗を詳細に見て行くと、強烈なのはほとんど新興のチェーン店化された他県の資本の飲食店です。新世界で味を守っている生え抜きの老舗はみんな静かに営業してます!数は少なくなってきましたが!
■新世界公園本通商店街01
典型的な大阪紹介アングルで撮影してみました。通天閣を背景にづぼらやの看板・・・いまや若い世代やファミリーにまで支持されている一大観光ゾーンです。しかし両サイドのお店の看板はまるで「アジア」ですね!そういえば昨夜も大阪は熱帯夜でした。
■通天閣本通・更級
粛々と営業を続けている「蕎麦の更科」です。ともかくうどん文化圏の大阪にあって、それもコテコテの新世界のど真ん中で江戸文化の象徴のような蕎麦屋を続けている気骨には感激いたします。店構えは江戸風、しかし味は納得の関西風味に仕上がっております。新興の「まやかし大阪コテコテデザイン」に負けないで末永く営業してください!
(20081025旅)



CMAの総会の後、大阪の仲間に連れて行って頂いた所です。
いや~いいですよ!
ここまで看板が道路にはみ出しているのは…。
それと、外壁という外壁全てが看板というのも迫力があっていいですよ!
ここまでいくともうアートの世界ですね。
威勢いいね。
こういうの好きです!
中途半端じゃなくて!
※ 『じゃんじゃん通り』 の詳細はこちら ⇒ 新世界編・ジャンジャン横丁
新世界公園通り商店街04・平野屋
大阪の正統派・立ち飲みの「平野屋」、営業中の姿です。
■ジャンジャン横丁・千成屋コーヒー
「なぜかこの手の商店街にはこの手のコーヒー店が必ずあります。そしてまたこの手のコーヒー店は必ず美味しい珈琲があります!」というのが商店街の定理です。この「角ゴシック」の愛想のない看板を見てください!シンプルイズベストです!
■ジャンジャン横丁・串かつ
ジャンジャン横丁と言えば2度漬け禁止の「串かつ」が有名です。特にこの商店街の「ちとせ」や「八重勝」は新世界正統派の串かつ店として古くから営業を続けています。よく見ればこの看板の「身体に優しい植物油を使用」には時代の趨勢を感じます。多分終戦後は、「身体に悪いから串かつは植物油で!」なんて事は夢にも考えなかったでしょうね!生きて行くだけで大変だったのですから。
■ジャンジャン横丁・王将
かの有名な坂田三吉が通っていた将棋会所です。この種のゲーセンの原型は囲碁・スマートボール等がこの商店街にあり、少し他の商店街とは異なる成り立ちを持っているようです。
※どちらかというと東京は浅草に近い雰囲気です!
店舗は閉鎖的ではなく外から観戦することが可能なつくりで、賭け将棋などが出来にくいシステムだと推測されます。ともかく客の年齢層が50歳以上で完璧な「シルバーゲーセン」です。
■ジャンジャン横丁・ホルモン道場
ここでも大阪闇市を発祥とする「ホルモン焼店」が存在し興味深い!この地区の事を時代の生き証人の高齢者に聞いてみるとやはり第2次大戦の空襲にて通天閣より南のこの地区一帯が焼夷弾にて被災したようで、どちらかといえば「ホルモン」とか「串かつ」や「すいとん」と言った飲食のバラック小屋が中心の小規模の闇市(闇飲食街)であったようです。
■新世界公園通商店街03・平野屋
新世界では知らない人のいない居酒屋の名店「平野屋」この日も夕刻からの開業で、昼間はこんな風ですが夜には立ち飲み客で店はあふれ帰ります。価格はリーズナブルな上に味のいい、大人の居酒屋です。やはり老舗は落ち着いている!
■新世界公園本通商店街02
この色彩感覚には驚きます。原色の洪水です!ここまで強烈なデザインが連続すると、かえって目立たないのではと言う気がします。人はこれを「大阪的デザイン」と言いますが果たして本当にそうなんでしょうか?この強烈な店舗を詳細に見て行くと、強烈なのはほとんど新興のチェーン店化された他県の資本の飲食店です。新世界で味を守っている生え抜きの老舗はみんな静かに営業してます!数は少なくなってきましたが!
■新世界公園本通商店街01
典型的な大阪紹介アングルで撮影してみました。通天閣を背景にづぼらやの看板・・・いまや若い世代やファミリーにまで支持されている一大観光ゾーンです。しかし両サイドのお店の看板はまるで「アジア」ですね!そういえば昨夜も大阪は熱帯夜でした。
■通天閣本通・更級
粛々と営業を続けている「蕎麦の更科」です。ともかくうどん文化圏の大阪にあって、それもコテコテの新世界のど真ん中で江戸文化の象徴のような蕎麦屋を続けている気骨には感激いたします。店構えは江戸風、しかし味は納得の関西風味に仕上がっております。新興の「まやかし大阪コテコテデザイン」に負けないで末永く営業してください!
(20081025旅)
2008年10月25日
ATRIO BICI CAFE
■『ATRIO BICI CAFE』 大阪

CMAの総会に行って、全国の仲間と入った所です。
公園からダイレクトに入れてしまうカフェの雰囲気が面白いので思わず写真を撮ってしまいました。
公園の周りには木がいっぱい植えられていて外で食べるには蚊がいっぱいいてしんどいと思いますが、店内から眺める分にはいいですね~。
そして、店内には自転車が並べられていて思わず欲しくなってしまうのがまたたまらなくいいのでした。
お店のHPをのぞくとその雰囲気がお分かり頂けると思います。
イタリアンが有名らしいのですが、カレーのランチを食べました。
※ 『ATRIO BICI CAFE』 の詳細はこちら ⇒ ATRIO BICI CAFE
靭(うつぼ)公園の自然に包まれて味わうコーヒー・ワインと極上パスタ&ピッツァ。
靭公園の緑に囲まれたイタリアンカフェ&BAR。
本格エスプレッソマシーンで淹れたおいしいコーヒーと腕利きシェフのイタリア料理
ソムリエ厳選のワイン、豊富なドリンクをご用意しております。
ランチ・カフェの普段使いからディナー本格コースまで幅広く対応。
ランチは5時までOK。
ちょっとしたパーティやウェディング2次会まで、パーティメニューもリーズナブルにご用意。
様々なシーンで使えるカフェです。
(20081024旅)

CMAの総会に行って、全国の仲間と入った所です。
公園からダイレクトに入れてしまうカフェの雰囲気が面白いので思わず写真を撮ってしまいました。
公園の周りには木がいっぱい植えられていて外で食べるには蚊がいっぱいいてしんどいと思いますが、店内から眺める分にはいいですね~。
そして、店内には自転車が並べられていて思わず欲しくなってしまうのがまたたまらなくいいのでした。
お店のHPをのぞくとその雰囲気がお分かり頂けると思います。
イタリアンが有名らしいのですが、カレーのランチを食べました。
※ 『ATRIO BICI CAFE』 の詳細はこちら ⇒ ATRIO BICI CAFE
靭(うつぼ)公園の自然に包まれて味わうコーヒー・ワインと極上パスタ&ピッツァ。
靭公園の緑に囲まれたイタリアンカフェ&BAR。
本格エスプレッソマシーンで淹れたおいしいコーヒーと腕利きシェフのイタリア料理
ソムリエ厳選のワイン、豊富なドリンクをご用意しております。
ランチ・カフェの普段使いからディナー本格コースまで幅広く対応。
ランチは5時までOK。
ちょっとしたパーティやウェディング2次会まで、パーティメニューもリーズナブルにご用意。
様々なシーンで使えるカフェです。
(20081024旅)
2008年01月30日
北谷アメリカンビレッジ
■『北谷アメリカンビレッジ』 沖縄



もともと興味が無かった所でしたが、TVの旅番組を観て見に行きたくなったので行ってみることにしたのです。
基本的にアメリカ統治みたいな所を毛嫌いしていたとも言っていいのかもしれない。
着いた特は土砂降りの中だったので、人はまばらでシ~ンとしていました。
建物や街並を見て日本とは全く違って新鮮な感じがしましたし、また外国人率も非常に高いのでなんだか違った国に紛れ込んでしまった様な気もしました。
雑貨屋さん、お土産屋さん、古着屋さん、お食事処、その他いろいろありましたが、とりあえずサ~ッと街並散策をして廻ることとしました。
途中、古着の 『MA-1』 を買おうかと思いましたが、高かったので止めました…。
古着が好きな人には楽しめますね、ちょっと高めだけど…。
個人的にはフラフラ散策するのにいい場所だと思いました。
※ 『北谷アメリカンビレッジ』 の詳細はこちら ⇒北谷アメリカンビレッジ
☆アメリカンビレッジって?
アメリカンビレッジは、那覇空港から車で約40分、沖縄本島中南部の北谷町美浜【ちゃたんちょうみはま】にあります。元々は米軍基地でしたが、その跡地を利用して建設された都市型リゾートです。 近隣には、野球場やサンセットビーチがあります。ビーチからの夕日の眺めは最高ですよ。。 設備も完備されてるのでチッエクしてみてはいかか?夏場はシーポート北谷カーニバルなどが行われます。
☆主な施設
アメリカンの雰囲気の中に数多くのショップやレストランなどが立ち並んでいます。大型スーパーを始め、ゲームセンター ボーリング場 映画館など遊べる おしゃれなショッピングゾーンです。
(20071227旅)



もともと興味が無かった所でしたが、TVの旅番組を観て見に行きたくなったので行ってみることにしたのです。
基本的にアメリカ統治みたいな所を毛嫌いしていたとも言っていいのかもしれない。
着いた特は土砂降りの中だったので、人はまばらでシ~ンとしていました。
建物や街並を見て日本とは全く違って新鮮な感じがしましたし、また外国人率も非常に高いのでなんだか違った国に紛れ込んでしまった様な気もしました。
雑貨屋さん、お土産屋さん、古着屋さん、お食事処、その他いろいろありましたが、とりあえずサ~ッと街並散策をして廻ることとしました。
途中、古着の 『MA-1』 を買おうかと思いましたが、高かったので止めました…。
古着が好きな人には楽しめますね、ちょっと高めだけど…。
個人的にはフラフラ散策するのにいい場所だと思いました。
※ 『北谷アメリカンビレッジ』 の詳細はこちら ⇒北谷アメリカンビレッジ
☆アメリカンビレッジって?
アメリカンビレッジは、那覇空港から車で約40分、沖縄本島中南部の北谷町美浜【ちゃたんちょうみはま】にあります。元々は米軍基地でしたが、その跡地を利用して建設された都市型リゾートです。 近隣には、野球場やサンセットビーチがあります。ビーチからの夕日の眺めは最高ですよ。。 設備も完備されてるのでチッエクしてみてはいかか?夏場はシーポート北谷カーニバルなどが行われます。
☆主な施設
アメリカンの雰囲気の中に数多くのショップやレストランなどが立ち並んでいます。大型スーパーを始め、ゲームセンター ボーリング場 映画館など遊べる おしゃれなショッピングゾーンです。
(20071227旅)
2008年01月22日
備瀬の福木並木
■『備瀬の福木並木』 沖縄


『美ら海水族館』 に行った後、ソーキソバを食べたくて近くをウロウロしていたら偶然見つけたスポットです。
今考えると何かに吸い寄せられて行った様な感じがします。
正直な感想としてはかなりのカルチャーショックを受けました…。
まだこういう生活をしている所があったんだ…完全に時間が止まってしまった様な気がしたのです。
『こういう沖縄らしい所に来たかった~!』 と、とても嬉しくもありました。
商売っ気の全く無いおじさんが引く馬車に揺られ、のんびりとした贅沢な一時を過ごすことが出来ました。
個人的には歩きより馬車の方が絶対にいいと思います!
馬は道端の草をたまに食べるので草むらにつっこっむのですが、それがまたたまらなくいいのです。
古き良き日本を感じられることが出来てとても感慨深かったです。
是非寄ってみて下さい!
今度行ったら、もう一度馬車に乗ってそして歩きで奥まで探検しようと思います。
※ 『備瀬の福木並木』 の詳細はこちら ⇒ 備瀬の福木並木
備瀬は福木の村である。屋敷という屋敷はみな福木の大木で囲まれ、東西南北には小路(スージ)が走り、南北をつらぬく大通りに平行して、その両側にも小路がのび、この三本の南北の通りに、東西の小路が交差して碁盤の目を形成しているのである。
備瀬の部落は中央の大通りにそって南北に伸び、南からしばらく行くと、そこが村の公民館前の広場(アシビナー)になっていて、雑貨店もある。
福木の向こう側から人の話し声が聞こえて来るときもあるが、備瀬はどこまでも福木の村である。家々のまわりに福木を植えたというよりも、福木林の中に村づくりをしたと言った方が適切かもしれない。 …
著:親泊元高 沖縄県建築士会会誌「沖縄建築士」(1972年7月発行・復帰記念特集号)より
(20071225旅)


『美ら海水族館』 に行った後、ソーキソバを食べたくて近くをウロウロしていたら偶然見つけたスポットです。
今考えると何かに吸い寄せられて行った様な感じがします。
正直な感想としてはかなりのカルチャーショックを受けました…。
まだこういう生活をしている所があったんだ…完全に時間が止まってしまった様な気がしたのです。
『こういう沖縄らしい所に来たかった~!』 と、とても嬉しくもありました。
商売っ気の全く無いおじさんが引く馬車に揺られ、のんびりとした贅沢な一時を過ごすことが出来ました。
個人的には歩きより馬車の方が絶対にいいと思います!
馬は道端の草をたまに食べるので草むらにつっこっむのですが、それがまたたまらなくいいのです。
古き良き日本を感じられることが出来てとても感慨深かったです。
是非寄ってみて下さい!
今度行ったら、もう一度馬車に乗ってそして歩きで奥まで探検しようと思います。
※ 『備瀬の福木並木』 の詳細はこちら ⇒ 備瀬の福木並木
備瀬は福木の村である。屋敷という屋敷はみな福木の大木で囲まれ、東西南北には小路(スージ)が走り、南北をつらぬく大通りに平行して、その両側にも小路がのび、この三本の南北の通りに、東西の小路が交差して碁盤の目を形成しているのである。
備瀬の部落は中央の大通りにそって南北に伸び、南からしばらく行くと、そこが村の公民館前の広場(アシビナー)になっていて、雑貨店もある。
福木の向こう側から人の話し声が聞こえて来るときもあるが、備瀬はどこまでも福木の村である。家々のまわりに福木を植えたというよりも、福木林の中に村づくりをしたと言った方が適切かもしれない。 …
著:親泊元高 沖縄県建築士会会誌「沖縄建築士」(1972年7月発行・復帰記念特集号)より
(20071225旅)
2008年01月19日
斎場御獄
■『斎場御獄』 (せーふぁうたき) 【世界遺産】 沖縄

ついに行くことが出来ました…琉球王国最高の聖地と言われている所です。
いままでTVで何回か見たことがあったのである程度は想像していたのですが、行って見るとやはりいいですね。
これで点と点が線で繋がった感じがします。
海から這い上がってくる風を体全体で感じられて良かったです。
沖縄に行かれる方には、是非行って欲しいスポットです。
※ 『斎場御獄』 の詳細はこちら ⇒ 斎場御獄
沖縄には、村や航海の無事を見守る神などがまつられている聖地(せいち)がたくさんありますが、これらをまとめて御嶽(うたき)とよんでいます。
その中でも斎場御嶽(せいふぁうたき)は、琉球王国でもっとも格式の高い聖地とされていました。
琉球王国時代、斎場御嶽では、神女でもっとも位の高い聞得大君(きこえおおきみ)の就任儀式『お新下り(おあらおり)』や、国の豊じょうや平和を願い、王様自らがお参りする『東御廻り(あがりうまい)』など、国の大切な神事がおこなわれていました。
当時は、王様や聞得大君など限られた人しか入ることができませんでしたが、今では一般の人でも入ることができるようになり、『東御廻り』の参拝者がたえずおとずれています。
(20071224旅)

ついに行くことが出来ました…琉球王国最高の聖地と言われている所です。
いままでTVで何回か見たことがあったのである程度は想像していたのですが、行って見るとやはりいいですね。
これで点と点が線で繋がった感じがします。
海から這い上がってくる風を体全体で感じられて良かったです。
沖縄に行かれる方には、是非行って欲しいスポットです。
※ 『斎場御獄』 の詳細はこちら ⇒ 斎場御獄
沖縄には、村や航海の無事を見守る神などがまつられている聖地(せいち)がたくさんありますが、これらをまとめて御嶽(うたき)とよんでいます。
その中でも斎場御嶽(せいふぁうたき)は、琉球王国でもっとも格式の高い聖地とされていました。
琉球王国時代、斎場御嶽では、神女でもっとも位の高い聞得大君(きこえおおきみ)の就任儀式『お新下り(おあらおり)』や、国の豊じょうや平和を願い、王様自らがお参りする『東御廻り(あがりうまい)』など、国の大切な神事がおこなわれていました。
当時は、王様や聞得大君など限られた人しか入ることができませんでしたが、今では一般の人でも入ることができるようになり、『東御廻り』の参拝者がたえずおとずれています。
(20071224旅)
2007年12月28日
『A&W』 と 『丸大』
■ 『A&W』 と 『丸大』
今回、うちの家族が沖縄到着後すぐに行った所はここでした。
通常の観光ルートとは全然違うでしょ!(笑)

『A&W』 でアメリカンなファーストフードをチョイス!
ハンバーガーの大きさは普通よりちょっと大きいくらいなのですが、ハンバーグとかのボリュームは満点でした。
そして、ルートビアというコーラみたいな飲み物がありこれは初のフィーリングでした。
(これはなんとお代わり無料なのです。)
カーリーフライ、スーパーフライはマックとかのフライドポテトとは違い、繊細な味がして美味しかったです。
初めて出会う形や味というものは単純にちょっぴり感動しますね。

スーパー 『丸大』 で地元の生活に密着…というか食べ物探訪。
我が家にとっては地元の食材を見るのがとても楽しみな一こまなのです。
『SPAM』 や 『さんぴん茶』 その他のお菓子等を沖縄価格でゲット!
いろいろな食材が売られていましたが、そんなに変わったものはありませんでした。
時期柄、クリスマス用品や正月用品も売っていましたね。
※ お店情報はこちら ⇒ 『A&W』
『丸大』
沖縄に誕生し地域と共に成長してきた私たちにとって何よりのよろこびは、お客様が笑顔と会話にあふれる食事を楽しんでいる姿を見ること。
会話に花が咲いたり、思わず笑顔が飛び出すような商品づくり・サービスに努めていきます。
1919年に、ロイ・アレン(Roy Allen)が、カルフォルニア州のロディで、ルートビアスタンドを開店したのがA&Wレストランの始まりです。アレンは、従業員であったフランク・ライト(Frank Wright)と提携してヒューストン(テキサス州)に3つの新しい店舗を作りました。そして2人は、ルートビアにA&Wの名前をつけました。
アレンは、A&Wドライブインや屋台等を開店する権利を与えるというアメリカで最初のフランチャイズレストランチェーンを作りました。それから8年の間に、アレンはアメリカの中西部を中心に、全国で171のフランチャイズ店を作りました。そして、1950年までには、450店のA&Wドライブインが開店したのです。
1963年に、A&W沖縄が屋宜原に日本初のファーストフードレストランを開店しました。ドライブインやアメリカンスタイルは、大人から子供まで大人気でした。
1974年には、A&Wのキャラクター、グレート・ルートビア(ベア君)が誕生。グランド・オープニングへの参加や、地域社会でのサービスを行っています。
(20071224旅)
今回、うちの家族が沖縄到着後すぐに行った所はここでした。
通常の観光ルートとは全然違うでしょ!(笑)

『A&W』 でアメリカンなファーストフードをチョイス!
ハンバーガーの大きさは普通よりちょっと大きいくらいなのですが、ハンバーグとかのボリュームは満点でした。
そして、ルートビアというコーラみたいな飲み物がありこれは初のフィーリングでした。
(これはなんとお代わり無料なのです。)
カーリーフライ、スーパーフライはマックとかのフライドポテトとは違い、繊細な味がして美味しかったです。
初めて出会う形や味というものは単純にちょっぴり感動しますね。

スーパー 『丸大』 で地元の生活に密着…というか食べ物探訪。
我が家にとっては地元の食材を見るのがとても楽しみな一こまなのです。
『SPAM』 や 『さんぴん茶』 その他のお菓子等を沖縄価格でゲット!
いろいろな食材が売られていましたが、そんなに変わったものはありませんでした。
時期柄、クリスマス用品や正月用品も売っていましたね。
※ お店情報はこちら ⇒ 『A&W』
『丸大』
沖縄に誕生し地域と共に成長してきた私たちにとって何よりのよろこびは、お客様が笑顔と会話にあふれる食事を楽しんでいる姿を見ること。
会話に花が咲いたり、思わず笑顔が飛び出すような商品づくり・サービスに努めていきます。
1919年に、ロイ・アレン(Roy Allen)が、カルフォルニア州のロディで、ルートビアスタンドを開店したのがA&Wレストランの始まりです。アレンは、従業員であったフランク・ライト(Frank Wright)と提携してヒューストン(テキサス州)に3つの新しい店舗を作りました。そして2人は、ルートビアにA&Wの名前をつけました。
アレンは、A&Wドライブインや屋台等を開店する権利を与えるというアメリカで最初のフランチャイズレストランチェーンを作りました。それから8年の間に、アレンはアメリカの中西部を中心に、全国で171のフランチャイズ店を作りました。そして、1950年までには、450店のA&Wドライブインが開店したのです。
1963年に、A&W沖縄が屋宜原に日本初のファーストフードレストランを開店しました。ドライブインやアメリカンスタイルは、大人から子供まで大人気でした。
1974年には、A&Wのキャラクター、グレート・ルートビア(ベア君)が誕生。グランド・オープニングへの参加や、地域社会でのサービスを行っています。
(20071224旅)
2007年08月30日
鳴子こけし
■『鳴子こけし』…首を回すとキュッキュッと音がするこけしは鳴子だけだそうです。

こけしの由来について、自分自身間違った解釈(デマの類を信じていた)をしていたので、ちょっと解説してみます。
※ 『こけし』 の解説はこちら ⇒ こけし『ウィキペディア(Wikipedia)』
こけしが生まれるには、主に次の三つの条件が必要だったと言われてる。一つ目は、木地師が山から降りて温泉地に定住し、湯治客の需要に直接触れるようになった事。二つ目は、赤物が伝えられた事。三つ目は、湯治習俗が一般農民に或る種の再生儀礼として定着した事。
赤物というのは赤い染料を使った玩具や土産物のこと、赤は疱瘡(天然痘)から守るといってこの赤物を喜んで買い求め、子供のもてあそび物にした。赤物玩具を作る人のことも、赤物玩具を背負って行商に売り歩く人のことも赤物師と呼んでいた。赤物のもっとも盛んな産地は、小田原から箱根にかけての一帯であり、その手法が江戸の末期、文化文政から天保の頃に東北に伝わった。東北の農民達がさかんに伊勢詣りや金比羅詣りに行って、その途上、小田原、箱根の木地玩具(赤物)を見るようになったのがその契機といわれる。湯治の農民達も土産物としてこの赤物の木地玩具を望むようになった。いままでお椀やお盆のように白木のまま出していた木地師が、色を付けた製品を出すようになるのは大きな変革であり、それは山の木地師が山から降りて湯治場に定着し、湯治客と直接接するようになって初めて起こったと考えられる。
当時の農民にとって湯治とは、厳しい作業の疲れを癒し、村落共同体の内外を問わず人々とのコミュニケーションを楽しむ重要な年中行事であった。事実上、農閑期以外に休日を持たない激務が続く中で、湯治場において得られる赤物こけしは心身回復のイメージと重ねられる縁起物でもあり、それを自らの家族の下へと運ぶ象徴的な形象であった。前述の通り、本来の用途は子供用の玩具であったにもかかわらず、現代においては一種の美術品としても見られる下地が存在するのはそのためである。 現在では江戸時代の末期、これら複数の条件が最も揃うと共に、冷害などのとりわけ過酷な環境の克服を余儀なくされ続けた東北地方において、こうしてこけしが発祥したものと考えられている。
また、あえて上記のような歴史的考察を無視し、「こけし」の起源を「子消し」に求めた説も一部に存在する。しかしそれらは何れも発音が似ている事以外に根拠を示す事が出来ず、広義の都市伝説とされる。
『第3回 こども絵付けコンクール』 が開催されていたので、投票して来ました。
アンパンマンこけし、ドラえもんこけし、仮面ライダーこけし、その他もろもろのこけしがあってとても面白かったです。
また、ここでは絵付けをしてオリジナルのこけしを製作することも出来ます。
プロの職人さんが指導して下さるので安心です。
※ 『こけし』 の詳細はこちら ⇒ 日本こけし館
■こけし館由来記
こけしの最も古い生産地、鳴子。
この地に日本こけし館が誕生したのは、昭和28年に詩人で童話作家の深澤要さんのコレクションが鳴子町に寄贈されたことと、昭和32年から毎年全国の工人たちからこけし祭りへの奉納こけしが贈り続けられたことが、大きなきっかけとなりました。
完成までに7年の歳月を費やし、昭和50年に開館。こけしをこよなく愛する人々の思いと夢が結実しました。
現在工人たちは全国各地に住み、それぞれの風土に溶け込みながらも、古来からの伝統を厳然と伝承しています。
日本こけし館には、このように広まった伝統こけしを一堂に集め受け継がれてきた素朴な心を、多くの方々に伝えたいという願いが込められています。
■こけしの歴史
今から約二百年前の文化・文政のころに奥山で木地業を生業とする人々が、我が子に与えたのが始まりと言われています。
その後山村の子供たちの玩具として愛されてきたこけしは、時代の流れとともに土産品として売られ大人の趣味・観賞用として発展しました。
東北各地の温泉地の木地師に伝承され現在では、11系統に分かれられ、その独特な東北人の人間性そのものが表れているといえます。
(20070827旅)

こけしの由来について、自分自身間違った解釈(デマの類を信じていた)をしていたので、ちょっと解説してみます。
※ 『こけし』 の解説はこちら ⇒ こけし『ウィキペディア(Wikipedia)』
こけしが生まれるには、主に次の三つの条件が必要だったと言われてる。一つ目は、木地師が山から降りて温泉地に定住し、湯治客の需要に直接触れるようになった事。二つ目は、赤物が伝えられた事。三つ目は、湯治習俗が一般農民に或る種の再生儀礼として定着した事。
赤物というのは赤い染料を使った玩具や土産物のこと、赤は疱瘡(天然痘)から守るといってこの赤物を喜んで買い求め、子供のもてあそび物にした。赤物玩具を作る人のことも、赤物玩具を背負って行商に売り歩く人のことも赤物師と呼んでいた。赤物のもっとも盛んな産地は、小田原から箱根にかけての一帯であり、その手法が江戸の末期、文化文政から天保の頃に東北に伝わった。東北の農民達がさかんに伊勢詣りや金比羅詣りに行って、その途上、小田原、箱根の木地玩具(赤物)を見るようになったのがその契機といわれる。湯治の農民達も土産物としてこの赤物の木地玩具を望むようになった。いままでお椀やお盆のように白木のまま出していた木地師が、色を付けた製品を出すようになるのは大きな変革であり、それは山の木地師が山から降りて湯治場に定着し、湯治客と直接接するようになって初めて起こったと考えられる。
当時の農民にとって湯治とは、厳しい作業の疲れを癒し、村落共同体の内外を問わず人々とのコミュニケーションを楽しむ重要な年中行事であった。事実上、農閑期以外に休日を持たない激務が続く中で、湯治場において得られる赤物こけしは心身回復のイメージと重ねられる縁起物でもあり、それを自らの家族の下へと運ぶ象徴的な形象であった。前述の通り、本来の用途は子供用の玩具であったにもかかわらず、現代においては一種の美術品としても見られる下地が存在するのはそのためである。 現在では江戸時代の末期、これら複数の条件が最も揃うと共に、冷害などのとりわけ過酷な環境の克服を余儀なくされ続けた東北地方において、こうしてこけしが発祥したものと考えられている。
また、あえて上記のような歴史的考察を無視し、「こけし」の起源を「子消し」に求めた説も一部に存在する。しかしそれらは何れも発音が似ている事以外に根拠を示す事が出来ず、広義の都市伝説とされる。
『第3回 こども絵付けコンクール』 が開催されていたので、投票して来ました。
アンパンマンこけし、ドラえもんこけし、仮面ライダーこけし、その他もろもろのこけしがあってとても面白かったです。
また、ここでは絵付けをしてオリジナルのこけしを製作することも出来ます。
プロの職人さんが指導して下さるので安心です。
※ 『こけし』 の詳細はこちら ⇒ 日本こけし館
■こけし館由来記
こけしの最も古い生産地、鳴子。
この地に日本こけし館が誕生したのは、昭和28年に詩人で童話作家の深澤要さんのコレクションが鳴子町に寄贈されたことと、昭和32年から毎年全国の工人たちからこけし祭りへの奉納こけしが贈り続けられたことが、大きなきっかけとなりました。
完成までに7年の歳月を費やし、昭和50年に開館。こけしをこよなく愛する人々の思いと夢が結実しました。
現在工人たちは全国各地に住み、それぞれの風土に溶け込みながらも、古来からの伝統を厳然と伝承しています。
日本こけし館には、このように広まった伝統こけしを一堂に集め受け継がれてきた素朴な心を、多くの方々に伝えたいという願いが込められています。
■こけしの歴史
今から約二百年前の文化・文政のころに奥山で木地業を生業とする人々が、我が子に与えたのが始まりと言われています。
その後山村の子供たちの玩具として愛されてきたこけしは、時代の流れとともに土産品として売られ大人の趣味・観賞用として発展しました。
東北各地の温泉地の木地師に伝承され現在では、11系統に分かれられ、その独特な東北人の人間性そのものが表れているといえます。
(20070827旅)
2007年08月29日
銀山温泉
■『銀山温泉』…大正ロマンの湯の街、風情を残す癒しの地です。


そこは想像していたほど奥まった場所ではなく、意外と街から近い場所にありました。
小さな川を挟んで木造の旅館が立ち並ぶ、よく雑誌で見かけるそのままの温泉地なのでした。
そして、建物はとても歴史を感じるものでした。
これから秋~冬にかけて、紅葉~雪景色とここに訪れる人の数は増えていくのだそうです。
温泉街にラーメン屋などというものは無く、硬派の温泉地といった感じがしました。
そして、その規模も小さいので旅館で借りた下駄をカタカタ鳴らして簡単に見て廻ることが出来ました。
他と比較すると、草津温泉とかだと温泉地の規模が大きいから、あれもこれも見ようとして疲れてしまいますが、ここではそういうことはありません。
ゆっくりと全てを程よく見て廻ることが出来るのです。
小さなお子さんやご老人がいても十分に雰囲気を満喫することが出来ます。
共同浴場が2軒あるのですが、ここはお奨めです!
ここは源泉100%なので一番効果がありそうな気がしました。
入湯料金200円と書いてありましたが、銀山温泉に泊まっているお客さんは払わなくて良いのだそうです。
そこを掃除しているらしいおじさんがおっしゃっていたので間違いないと思うのですが、確かではありません。
一応ご確認の上、入湯して下さい!
ちなみにうちらはその有難いお言葉を信じて払わずに入って来ました。
また、ここへ行ったら銀山跡への散策も是非して下さい。
1689年に廃山になったとのことなのでもう300年以上も前の遺構です。
冬はこの散策がとても大変らしくカンジキを履いていくらしい。
途中にある『夏しらず坑』はとても涼しく、こんなエアコンが家にあったらいいのにと痛切に感じました。
反対側にある穴から入った風が洞窟の中を通って心地良く冷えた温度になって出て来るのでしょう。
今度は是非とも冬景色を見に行きたいものである…。
※ 『銀山温泉』 の詳細はこちら ⇒ 銀山温泉組合 公式サイト
静かに流れる銀山川をはさんで並ぶ、木造りの旅館の数々・・・
三層、四層にかさなる屋根のひとつひとつに、銀山の歴史が宿っています。
湯けむりがつなぐ時間の扉を開けるとそこは古き良き時代。
地酒を飲み交わす杯で、銀鉱が栄えていた頃の鉱夫たちの夢を計り、心癒されるひとときに優しい浪漫の風を感じて下さい。
(20070828旅)


そこは想像していたほど奥まった場所ではなく、意外と街から近い場所にありました。
小さな川を挟んで木造の旅館が立ち並ぶ、よく雑誌で見かけるそのままの温泉地なのでした。
そして、建物はとても歴史を感じるものでした。
これから秋~冬にかけて、紅葉~雪景色とここに訪れる人の数は増えていくのだそうです。
温泉街にラーメン屋などというものは無く、硬派の温泉地といった感じがしました。
そして、その規模も小さいので旅館で借りた下駄をカタカタ鳴らして簡単に見て廻ることが出来ました。
他と比較すると、草津温泉とかだと温泉地の規模が大きいから、あれもこれも見ようとして疲れてしまいますが、ここではそういうことはありません。
ゆっくりと全てを程よく見て廻ることが出来るのです。
小さなお子さんやご老人がいても十分に雰囲気を満喫することが出来ます。
共同浴場が2軒あるのですが、ここはお奨めです!
ここは源泉100%なので一番効果がありそうな気がしました。
入湯料金200円と書いてありましたが、銀山温泉に泊まっているお客さんは払わなくて良いのだそうです。
そこを掃除しているらしいおじさんがおっしゃっていたので間違いないと思うのですが、確かではありません。
一応ご確認の上、入湯して下さい!
ちなみにうちらはその有難いお言葉を信じて払わずに入って来ました。
また、ここへ行ったら銀山跡への散策も是非して下さい。
1689年に廃山になったとのことなのでもう300年以上も前の遺構です。
冬はこの散策がとても大変らしくカンジキを履いていくらしい。
途中にある『夏しらず坑』はとても涼しく、こんなエアコンが家にあったらいいのにと痛切に感じました。
反対側にある穴から入った風が洞窟の中を通って心地良く冷えた温度になって出て来るのでしょう。
今度は是非とも冬景色を見に行きたいものである…。
※ 『銀山温泉』 の詳細はこちら ⇒ 銀山温泉組合 公式サイト
静かに流れる銀山川をはさんで並ぶ、木造りの旅館の数々・・・
三層、四層にかさなる屋根のひとつひとつに、銀山の歴史が宿っています。
湯けむりがつなぐ時間の扉を開けるとそこは古き良き時代。
地酒を飲み交わす杯で、銀鉱が栄えていた頃の鉱夫たちの夢を計り、心癒されるひとときに優しい浪漫の風を感じて下さい。
(20070828旅)