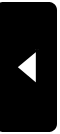2008年12月27日
やちむんの里-1
■『やちむんの里』 沖縄 読谷村





ここは前回訪れることが出来なかった場所です。
今回、大人の楽しみ・テーマとして 『気に入った焼物があったら買って来よう!』 ということがありました。
なるほど…この地域全体が焼物の村といった感じでした。
この里の入口にはきれいな駐車場が整備されていて、里内は歩いて散策をすることが出来ます。
焼物に興味のある方だったら半日では足りないかもしれません…。
うちは小さい子がいるから、1時間程でちょこっと廻って気に入った物を買って来ました。 (雨もパラパラしていたし…)
購入した物は、頑なな伝統を受け継いでいる物とは少し違って伝統を受け継ぎつつもポップ感を感じられる物です。
事務所&家にお越しの際はこの器でお茶を入れさせて頂くかもしれません…楽しみにしていて下さい!
※ 『やちむんの里』 の詳細はこちら ⇒ やちむんの里
「やちむん」とは沖縄で焼物のことで、やちむんの里は陶芸家の方々が集まってできました。里では作品を作っているところを見ることができたり、やちむんの販売や、やちむんの器で食事をとることもできます。自然に囲まれた美術館にいるような感じがします。
■沖縄の焼物は、力強く暖かいものが多いです。
1682年の頃、琉球王朝の尚貞王は、各地に点在した窯場を壺屋に集めて陶業の進行を図りました。そして、今まであった技術に加え、日本、中国各地の技術を吸収しながら多彩な焼き物を作っていきます。
現在でも、那覇の壺屋には多くの焼き物やが軒を並べ、登り窯の跡などもあり、当時の繁栄を時間を超えて垣間見る事が出来ます。
ただ、最近では住宅が密集してきたので、焼き物を焼くには環境的に無理が生じてきたために窯場は読谷村の座喜味城跡の近くにあるやちむんの里の方に移っています。
人間国宝の金城次郎氏が招致され、「やちむんの里」構想に何人かの陶芸家達が共同登り窯をつくり、その後若手の陶工が読谷山焼「北窯」として独立、現在は何軒のも工房が立ち並び、各々売店、展示場などが併設されて週末には、この山間の里に来る人々も増えています。
(20081225旅)





ここは前回訪れることが出来なかった場所です。
今回、大人の楽しみ・テーマとして 『気に入った焼物があったら買って来よう!』 ということがありました。
なるほど…この地域全体が焼物の村といった感じでした。
この里の入口にはきれいな駐車場が整備されていて、里内は歩いて散策をすることが出来ます。
焼物に興味のある方だったら半日では足りないかもしれません…。
うちは小さい子がいるから、1時間程でちょこっと廻って気に入った物を買って来ました。 (雨もパラパラしていたし…)
購入した物は、頑なな伝統を受け継いでいる物とは少し違って伝統を受け継ぎつつもポップ感を感じられる物です。
事務所&家にお越しの際はこの器でお茶を入れさせて頂くかもしれません…楽しみにしていて下さい!
※ 『やちむんの里』 の詳細はこちら ⇒ やちむんの里
「やちむん」とは沖縄で焼物のことで、やちむんの里は陶芸家の方々が集まってできました。里では作品を作っているところを見ることができたり、やちむんの販売や、やちむんの器で食事をとることもできます。自然に囲まれた美術館にいるような感じがします。
■沖縄の焼物は、力強く暖かいものが多いです。
1682年の頃、琉球王朝の尚貞王は、各地に点在した窯場を壺屋に集めて陶業の進行を図りました。そして、今まであった技術に加え、日本、中国各地の技術を吸収しながら多彩な焼き物を作っていきます。
現在でも、那覇の壺屋には多くの焼き物やが軒を並べ、登り窯の跡などもあり、当時の繁栄を時間を超えて垣間見る事が出来ます。
ただ、最近では住宅が密集してきたので、焼き物を焼くには環境的に無理が生じてきたために窯場は読谷村の座喜味城跡の近くにあるやちむんの里の方に移っています。
人間国宝の金城次郎氏が招致され、「やちむんの里」構想に何人かの陶芸家達が共同登り窯をつくり、その後若手の陶工が読谷山焼「北窯」として独立、現在は何軒のも工房が立ち並び、各々売店、展示場などが併設されて週末には、この山間の里に来る人々も増えています。
(20081225旅)
Posted by kon at 17:37│Comments(0)
│街並探訪