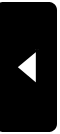2007年08月30日
鳴子こけし
■『鳴子こけし』…首を回すとキュッキュッと音がするこけしは鳴子だけだそうです。

こけしの由来について、自分自身間違った解釈(デマの類を信じていた)をしていたので、ちょっと解説してみます。
※ 『こけし』 の解説はこちら ⇒ こけし『ウィキペディア(Wikipedia)』
こけしが生まれるには、主に次の三つの条件が必要だったと言われてる。一つ目は、木地師が山から降りて温泉地に定住し、湯治客の需要に直接触れるようになった事。二つ目は、赤物が伝えられた事。三つ目は、湯治習俗が一般農民に或る種の再生儀礼として定着した事。
赤物というのは赤い染料を使った玩具や土産物のこと、赤は疱瘡(天然痘)から守るといってこの赤物を喜んで買い求め、子供のもてあそび物にした。赤物玩具を作る人のことも、赤物玩具を背負って行商に売り歩く人のことも赤物師と呼んでいた。赤物のもっとも盛んな産地は、小田原から箱根にかけての一帯であり、その手法が江戸の末期、文化文政から天保の頃に東北に伝わった。東北の農民達がさかんに伊勢詣りや金比羅詣りに行って、その途上、小田原、箱根の木地玩具(赤物)を見るようになったのがその契機といわれる。湯治の農民達も土産物としてこの赤物の木地玩具を望むようになった。いままでお椀やお盆のように白木のまま出していた木地師が、色を付けた製品を出すようになるのは大きな変革であり、それは山の木地師が山から降りて湯治場に定着し、湯治客と直接接するようになって初めて起こったと考えられる。
当時の農民にとって湯治とは、厳しい作業の疲れを癒し、村落共同体の内外を問わず人々とのコミュニケーションを楽しむ重要な年中行事であった。事実上、農閑期以外に休日を持たない激務が続く中で、湯治場において得られる赤物こけしは心身回復のイメージと重ねられる縁起物でもあり、それを自らの家族の下へと運ぶ象徴的な形象であった。前述の通り、本来の用途は子供用の玩具であったにもかかわらず、現代においては一種の美術品としても見られる下地が存在するのはそのためである。 現在では江戸時代の末期、これら複数の条件が最も揃うと共に、冷害などのとりわけ過酷な環境の克服を余儀なくされ続けた東北地方において、こうしてこけしが発祥したものと考えられている。
また、あえて上記のような歴史的考察を無視し、「こけし」の起源を「子消し」に求めた説も一部に存在する。しかしそれらは何れも発音が似ている事以外に根拠を示す事が出来ず、広義の都市伝説とされる。
『第3回 こども絵付けコンクール』 が開催されていたので、投票して来ました。
アンパンマンこけし、ドラえもんこけし、仮面ライダーこけし、その他もろもろのこけしがあってとても面白かったです。
また、ここでは絵付けをしてオリジナルのこけしを製作することも出来ます。
プロの職人さんが指導して下さるので安心です。
※ 『こけし』 の詳細はこちら ⇒ 日本こけし館
■こけし館由来記
こけしの最も古い生産地、鳴子。
この地に日本こけし館が誕生したのは、昭和28年に詩人で童話作家の深澤要さんのコレクションが鳴子町に寄贈されたことと、昭和32年から毎年全国の工人たちからこけし祭りへの奉納こけしが贈り続けられたことが、大きなきっかけとなりました。
完成までに7年の歳月を費やし、昭和50年に開館。こけしをこよなく愛する人々の思いと夢が結実しました。
現在工人たちは全国各地に住み、それぞれの風土に溶け込みながらも、古来からの伝統を厳然と伝承しています。
日本こけし館には、このように広まった伝統こけしを一堂に集め受け継がれてきた素朴な心を、多くの方々に伝えたいという願いが込められています。
■こけしの歴史
今から約二百年前の文化・文政のころに奥山で木地業を生業とする人々が、我が子に与えたのが始まりと言われています。
その後山村の子供たちの玩具として愛されてきたこけしは、時代の流れとともに土産品として売られ大人の趣味・観賞用として発展しました。
東北各地の温泉地の木地師に伝承され現在では、11系統に分かれられ、その独特な東北人の人間性そのものが表れているといえます。
(20070827旅)

こけしの由来について、自分自身間違った解釈(デマの類を信じていた)をしていたので、ちょっと解説してみます。
※ 『こけし』 の解説はこちら ⇒ こけし『ウィキペディア(Wikipedia)』
こけしが生まれるには、主に次の三つの条件が必要だったと言われてる。一つ目は、木地師が山から降りて温泉地に定住し、湯治客の需要に直接触れるようになった事。二つ目は、赤物が伝えられた事。三つ目は、湯治習俗が一般農民に或る種の再生儀礼として定着した事。
赤物というのは赤い染料を使った玩具や土産物のこと、赤は疱瘡(天然痘)から守るといってこの赤物を喜んで買い求め、子供のもてあそび物にした。赤物玩具を作る人のことも、赤物玩具を背負って行商に売り歩く人のことも赤物師と呼んでいた。赤物のもっとも盛んな産地は、小田原から箱根にかけての一帯であり、その手法が江戸の末期、文化文政から天保の頃に東北に伝わった。東北の農民達がさかんに伊勢詣りや金比羅詣りに行って、その途上、小田原、箱根の木地玩具(赤物)を見るようになったのがその契機といわれる。湯治の農民達も土産物としてこの赤物の木地玩具を望むようになった。いままでお椀やお盆のように白木のまま出していた木地師が、色を付けた製品を出すようになるのは大きな変革であり、それは山の木地師が山から降りて湯治場に定着し、湯治客と直接接するようになって初めて起こったと考えられる。
当時の農民にとって湯治とは、厳しい作業の疲れを癒し、村落共同体の内外を問わず人々とのコミュニケーションを楽しむ重要な年中行事であった。事実上、農閑期以外に休日を持たない激務が続く中で、湯治場において得られる赤物こけしは心身回復のイメージと重ねられる縁起物でもあり、それを自らの家族の下へと運ぶ象徴的な形象であった。前述の通り、本来の用途は子供用の玩具であったにもかかわらず、現代においては一種の美術品としても見られる下地が存在するのはそのためである。 現在では江戸時代の末期、これら複数の条件が最も揃うと共に、冷害などのとりわけ過酷な環境の克服を余儀なくされ続けた東北地方において、こうしてこけしが発祥したものと考えられている。
また、あえて上記のような歴史的考察を無視し、「こけし」の起源を「子消し」に求めた説も一部に存在する。しかしそれらは何れも発音が似ている事以外に根拠を示す事が出来ず、広義の都市伝説とされる。
『第3回 こども絵付けコンクール』 が開催されていたので、投票して来ました。
アンパンマンこけし、ドラえもんこけし、仮面ライダーこけし、その他もろもろのこけしがあってとても面白かったです。
また、ここでは絵付けをしてオリジナルのこけしを製作することも出来ます。
プロの職人さんが指導して下さるので安心です。
※ 『こけし』 の詳細はこちら ⇒ 日本こけし館
■こけし館由来記
こけしの最も古い生産地、鳴子。
この地に日本こけし館が誕生したのは、昭和28年に詩人で童話作家の深澤要さんのコレクションが鳴子町に寄贈されたことと、昭和32年から毎年全国の工人たちからこけし祭りへの奉納こけしが贈り続けられたことが、大きなきっかけとなりました。
完成までに7年の歳月を費やし、昭和50年に開館。こけしをこよなく愛する人々の思いと夢が結実しました。
現在工人たちは全国各地に住み、それぞれの風土に溶け込みながらも、古来からの伝統を厳然と伝承しています。
日本こけし館には、このように広まった伝統こけしを一堂に集め受け継がれてきた素朴な心を、多くの方々に伝えたいという願いが込められています。
■こけしの歴史
今から約二百年前の文化・文政のころに奥山で木地業を生業とする人々が、我が子に与えたのが始まりと言われています。
その後山村の子供たちの玩具として愛されてきたこけしは、時代の流れとともに土産品として売られ大人の趣味・観賞用として発展しました。
東北各地の温泉地の木地師に伝承され現在では、11系統に分かれられ、その独特な東北人の人間性そのものが表れているといえます。
(20070827旅)
Posted by kon at 09:12│Comments(0)
│街並探訪