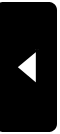2006年12月11日
飛騨高山-日下部家
■『日下部家』 飛騨高山




日下部家は、『国指定 重要文化財』の建物で、高山の町並より少し外れた北側にあります。
建築が好きな人は、高山の町並もいいですが、ここは押さえておかないとダメなんです。
外国人観光客はたくさんいますが、日本人はどうしてか?あまり知られていないようです…。
【ちょっと解説】…下記HPより抜粋しました。
●町衆の文化
高山は、もと戦国の武将金森長近3万8千石の城下町であったが、元禄5年(1692)金森氏は国替えとなり、飛騨は徳川幕府直轄の天領となった。それ以来高山は、町人の町として栄えたのである。したがって、いまに見る高山の伝統は、武家文化中心のものではなく、町衆文化であった。
●代表的な町屋造り 日下部家住宅
日下部家は、天領時代幕府(代官所)の御用商人として栄えた商家で、屋号を「谷屋」といい、嘉永5年には、役所の御用金を用立てする掛屋〈かけや〉をつとめ、後には両替屋を営んだ。
当時の邸宅は、明治8年の大火で類焼し、4年後の明治12年(1879)に完成したのが、現在の建物である。棟梁〈とうりょう〉は当時の名工川尻治助で、彼は自己の技量をこの家に傾注し、江戸時代の建築様式そのままの、みごとな住宅を造り上げた。
主家〈おもや〉は、切妻造り段違い二階建て、一部吹き抜けの総桧〈ひのき〉造り。梁〈はり〉と束柱〈つかばしら〉の木組みの力強い構成、屋根の勾配〈こうばい〉はゆるく、軒〈のき〉の出は深い。また家の正面表構えの出格子〈こうし〉、入格子、窓切りの変化、ベンガラに煤〈すす〉をまぜて焦〈こげ〉茶色に塗った木部の仕上げ等、江戸時代高山の町家造りの特色を留めている。他に土蔵二棟がある。
昭和41年、明治建築の民家として、初めて国の重要文化財に指定され、以後民芸館として一般に公開している。
※『日下部家』の詳細はこちら ⇒ 日下部民藝館




日下部家は、『国指定 重要文化財』の建物で、高山の町並より少し外れた北側にあります。
建築が好きな人は、高山の町並もいいですが、ここは押さえておかないとダメなんです。
外国人観光客はたくさんいますが、日本人はどうしてか?あまり知られていないようです…。
【ちょっと解説】…下記HPより抜粋しました。
●町衆の文化
高山は、もと戦国の武将金森長近3万8千石の城下町であったが、元禄5年(1692)金森氏は国替えとなり、飛騨は徳川幕府直轄の天領となった。それ以来高山は、町人の町として栄えたのである。したがって、いまに見る高山の伝統は、武家文化中心のものではなく、町衆文化であった。
●代表的な町屋造り 日下部家住宅
日下部家は、天領時代幕府(代官所)の御用商人として栄えた商家で、屋号を「谷屋」といい、嘉永5年には、役所の御用金を用立てする掛屋〈かけや〉をつとめ、後には両替屋を営んだ。
当時の邸宅は、明治8年の大火で類焼し、4年後の明治12年(1879)に完成したのが、現在の建物である。棟梁〈とうりょう〉は当時の名工川尻治助で、彼は自己の技量をこの家に傾注し、江戸時代の建築様式そのままの、みごとな住宅を造り上げた。
主家〈おもや〉は、切妻造り段違い二階建て、一部吹き抜けの総桧〈ひのき〉造り。梁〈はり〉と束柱〈つかばしら〉の木組みの力強い構成、屋根の勾配〈こうばい〉はゆるく、軒〈のき〉の出は深い。また家の正面表構えの出格子〈こうし〉、入格子、窓切りの変化、ベンガラに煤〈すす〉をまぜて焦〈こげ〉茶色に塗った木部の仕上げ等、江戸時代高山の町家造りの特色を留めている。他に土蔵二棟がある。
昭和41年、明治建築の民家として、初めて国の重要文化財に指定され、以後民芸館として一般に公開している。
※『日下部家』の詳細はこちら ⇒ 日下部民藝館
Posted by kon at 20:12│Comments(0)
│街並探訪